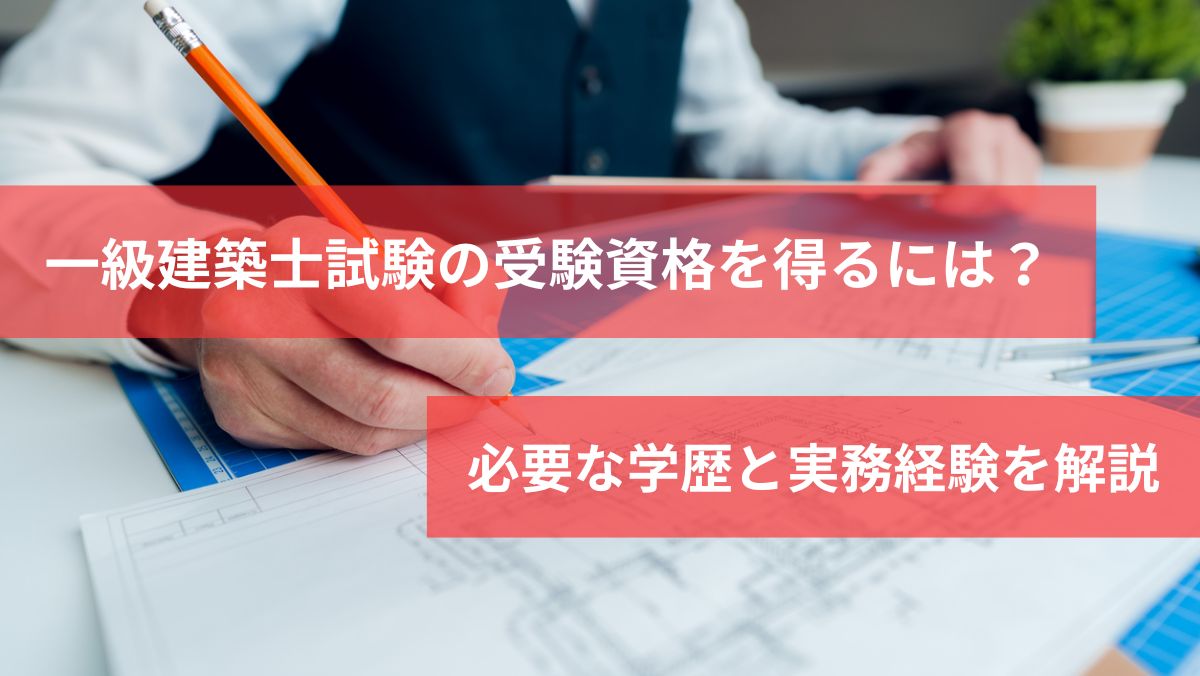設計から工事監理まで、建築プロジェクト全体を統括できる専門家である一級建築士。高い報酬と社会的信用を得られる一方で、その試験は非常に難易度が高いことでも知られています。
しかし、一級建築士を目指す上で、受験資格の要件を満たすことは試験合格と同じくらい重要です。学歴と実務経験の両方の要件をクリアしなければ、そもそも受験の機会すら得られません。
本記事では、一級建築士試験の受験資格について詳しく解説。一級建築士の魅力とともに、受験に必要な学歴や実務経験をご紹介します。
目次
一級建築士とは

一級建築士は、建築物の設計や工事監理を行う国家資格です。
建築士法に基づいて定められた資格で、一級建築士試験に合格し、一定の実務経験を積んだ後に登録申請を行うことで資格を取得できます。
一級建築士は二級建築士や木造建築士よりも上位の資格で、より高度で規模の大きな建築物を扱うことができます。
一級建築士の受験資格
一級建築士試験の受験資格は、学歴または持っている資格と、建築や土木に関する学科の単位の取得数によって異なります。
なお、受験資格を得て合格しても、所定の実務年数を満たさないと免許の申請はできません。
学歴
二級建築士や建築設備士の資格を持っていない場合で一級建築士試験を受験するためには、学歴で受験資格が判断されます。
なお、学歴の受験資格は「改正建築士法」適用以前の平成21年より前の大学入学者と平成21年以降の入学者で分かれています。
平成20年以前の入学者の場合、公益財団法人建築技術教育普及センターが認定した学校を卒業している人しか受験資格はありません。
学校名に「建築」などが入っていても、指定校でない場合があります。
一方、平成21年以降の入学者は指定科目を履修しているかが判定の基準となります。
法改正以降は4年制大学以外にも、職業能力開発総合大学校や短大、専修学校、高等学校などでも受験資格を得ることが可能となっています。
二級建築士
二級建築士の資格を持っている人も、一級建築士試験の受験資格を得ることができます。
受験資格には実務経験は必要ありません。つまり、二級建築士の試験に合格後、すぐに一級建築士の資格試験を得られるということです。
ただし、資格取得には二級建築士の資格取得から4年の実務経験を積む必要があります。
建築設備士
建築設備士の資格保有者も、一級建築士試験の受験資格を得ることができます。
建築設備士は、建築物の設備に関する専門家で建築士が設計した建物に、快適で安全な設備を配置するための「専門家」のような存在です。
建築設備士が空調、換気、給排水衛生、電気など、建物の設備に関する専門的な知識を持ち、建築設備を担当する一方で、
建築士は建物の設計、工事監理を行い、建築士が設計した建物に、快適で安全な設備を配置するための「専門家」のような存在といえるでしょう。
【試験合格後】 一級建築士の資格取得に必要な実務経験

先述した通り、一級建築士試験に合格後は、建築に関する実務経験を積まないと一級建築士として免許登録することはできません。
なお、以前は受験資格を得たあとに実務経験を積まないと試験を受けることができませんでしたが、現在は試験合格後に実務経験を積むことが可能となっています。
大学卒業者の場合
大学を卒業した後、一級建築士の資格を取得するためには、合計2年以上の実務経験が必要です。
この実務経験は、建築設計や工事監理などの建築関連業務に従事することで積むことができます。
実務経験の期間中は、様々な建築プロジェクトに携わり、実践的な知識とスキルを身につけることが重要です。
短期大学・高等専門学校卒業者の場合
短期大学(3年制)を卒業した場合は3年以上、短期大学(2年制)または高等専門学校を卒業した場合は4年以上の実務経験が必要となります。
この実務経験期間の違いは、教育課程の長さや内容の違いを考慮したもの。
実務経験を積む中で、学校で学んだ理論を実践に活かし、より深い専門知識を獲得することが期待されます。
二級建築士・建築設備士の場合
二級建築士と建築設備士の場合、それぞれ
- 二級建築士として4年以上
- 建築設備士として4年以上
の実務経験が必要となります。
受験資格を得るための方法
先述してきた通り、一級建築士試験の受験資格を得るためには、大学などに入学して指定された科目の単位を取得するか、二級建築士または建築設備士の資格を取得する方法があります。
大学などに入学する
大学や専門学校などの建築関連学科に入学し、指定科目を修めて卒業することで一級建築士試験の受験資格を得ることができます。
具体的には、建築学科や土木工学科のある大学がおすすめです。
取得すべき必要科目は建築設計製図、建築計画、建築環境工学、建築設備、構造力学、建築一般構造、建築材料、建築生産、建築法規、複合・関連科目です。
大学卒業後は、実務経験なしで一級建築士試験を受験することが可能です。ただし、免許登録には卒業後2年間の実務経験が必要となります。
この方法のメリットは、学生時代から専門的な知識を体系的に学べること。
また、最短で資格取得を目指せる点も魅力的です。
二級建築士または建築設備士の資格を取得する
二級建築士または建築設備士の資格を取得することで、一級建築士試験の受験資格を得ることができます。
二級建築士の場合、建築関係の学歴がなくても7年以上の実務経験を積むことで受験資格を得られます。
建築設備士も同様に、学歴や資格がなくても一定期間の実務経験で受験資格を得られます。
この方法のメリットは、大学などに通わずに資格取得を目指せる点です。実務経験を積みながら段階的に上位資格を目指すことができます。
ただし、二級建築士や建築設備士の試験自体も難易度が高く、合格率は低いため、十分な準備が必要です。
また、一級建築士試験の受験資格を得るまでに時間がかかる可能性があります。
いずれの方法を選択する場合も、一級建築士試験は難関であり、十分な学習と準備が必要となります。
あなたにぴったりの求人を無料で提案!登録してチャンスを広げよう
一級建築士の勉強スケジュールの例

二級建築士の資格取得を目指す場合、効果的な勉強スケジュールを立てることが重要です。一般的に、試験の約1年前から本格的な勉強を始めることをおすすめします。
最初の3ヶ月は基礎知識の習得に充て、その後6ヶ月間で各科目の深い理解と問題演習を行います。試験直前の3ヶ月は、苦手分野の克服と過去問演習に集中します。
毎日2〜3時間の学習時間を確保し、週末にはより長時間の学習セッションを設けることで、着実に知識を積み重ねていくことができます。
今よりもっと良い職場がきっと見つかる!登録して新しい求人情報を待つ
一級建築士資格取得のメリット

一級建築士の資格を取得すると、以下のようなメリットがあります。
資格手当により収入がアップする
一級建築士の資格を取得すると、多くの企業で資格手当が支給されます。この手当は月額数千円から数万円程度で、年収にすると数十万円の増加につながる可能性があります。
資格手当は、専門的な知識と技能を持つ一級建築士の価値を企業が認めているからこそ支給されるものです。
また、資格取得によって昇給や昇進のチャンスも増えるため、長期的な収入アップにつながります。
一級建築士の資格を活かせる仕事に就ける
一級建築士の資格は、建築設計事務所やゼネコン、ハウスメーカーなど、建築業界の様々な分野で高く評価されます。
この資格を持つことで、大規模プロジェクトの設計や管理職としての役割を任されるなど、より責任のある立場で仕事をする機会が増えます。
また、公共事業の入札参加資格として一級建築士が必要とされることも多いため、キャリアの幅が大きく広がります。
さらに、独立して自身の設計事務所を開業する際にも、一級建築士の資格は大きな強みとなります。
また、CADオペレーターとして働くことも可能です。CADオペレーターは、建築設計や構造設計において重要な役割を果たし、
一級建築士の資格を持つ者は単なる図面作成だけでなく、高度な専門知識を活かした設計支援が可能となります。
具体的な業務内容には、建築図面の作成と修正、3Dモデリングによる建築物の可視化、構造計算に基づいた詳細図面の作成、法規制に準拠した設計の確認などが含まれます。
一級建築士の資格を持つCADオペレーターは、設計者の意図を正確に理解し、効率的かつ高品質な図面作成が可能です。
また、建築プロジェクトの全体像を把握し、問題点の早期発見や改善提案を行うことができるため、プロジェクトの円滑な進行に貢献できます。
この職種では、最新のCADソフトウェアの操作スキルと建築に関する深い知識が求められますが、一級建築士の資格はそれらの要求を満たす強力な裏付けとなるでしょう。
CADオペレーターとして働くならアットキャド

アットキャドは、業界トップクラスの求人数を持つ、CADオペレーターやBIMオペレーターに特化した人材派遣・人材紹介サービスです。
20年以上の実績を持ち、スーパーゼネコンや大手設計事務所を含む2,600社以上と取引実績があり、業界トップクラスの求人数を誇ります。自社に設計部を設けているため、実際に図面を描くプロフェッショナルが在籍し、迅速なサポートが可能です。
研修制度も充実しており、初心者から経験者まで幅広く対応。登録から就業後まで徹底したフォローを行いますので安心してお仕事を探すことができます。
さらに、業界トップクラスの求人数があることから、転職のサポートも行っています。未経験からCADオペレーターやBIMオペレーターになりたい場合や、CADオペレーター・BIMオペレーターとしてキャリアアップしたい場合など、さまざまなケースに対応しているので、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
一級建築士の受験資格を得るためには、適切な学歴や実務経験が必要です。
大学や専門学校で建築関連の課程を修了するか、二級建築士や建築設備士の資格を取得し、必要な実務経験を積むことで受験資格を得ることができます。
資格取得後は、収入アップや幅広いキャリア選択肢など、多くのメリットが待っています。
一級建築士を目指す過程は長く厳しいものですが、建築業界でのキャリアを大きく飛躍させる重要なステップとなります。
自分の状況に合わせて最適な方法を選び、計画的に準備を進めることで、一級建築士という高度な専門資格の取得を実現させましょう。
▼コチラの記事もおすすめ