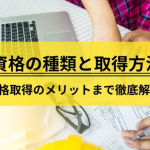建築業界において、建築士と設計士は非常に重要な役割を果たす職業です。
建物の設計や施工に関わるこれらの職種は、一見似ているようで実は大きな違いがありますがふたつの職業の明確な違いが分からないという方や、自分にどちらの職業が合っているのか迷っている方もいるでしょう。
本記事では、建築士と設計士の違いについて、資格、仕事内容、キャリアなどの観点から詳しく比較し、解説していきます。
目次
建築士と設計士の基本的な違い
まずは建築士と設計士の基本的な違いをご紹介します。
定義と法的位置づけ
建築士と設計士の最も基本的な違いは、その定義と法的位置づけにあります。
建築士は、建築基準法や建築士法によって明確に定義された国家資格です。一方、設計士は法的な定義のない職種であり、業界での一般的な認識や役割によって位置づけられています。
建築士は、建築物の設計や工事監理を行う専門家として法律で認められた資格です。建築士法によって、その業務範囲や責任が明確に定められており、建築確認申請書への署名や押印など、法的な権限を持っています。
これに対し、設計士は法律で定められた資格ではないため、そのような法的権限はありません。
資格の有無と種類
建築士には、一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類があります。これらの資格は、それぞれ異なる要件と試験によって取得することができます。
一級建築士は、最も高度な資格であり、あらゆる規模と用途の建築物の設計・工事監理を行うことができます。二級建築士は、一定規模以下の建築物を扱うことができ、木造建築士は主に木造建築物を対象としています。
一級建築士になるためには、建築学科を卒業後、実務経験を積んだ上で国家試験に合格する必要があります。二級建築士と木造建築士は建築士に関する科目を履修していれば実務経験は必要ありませんが、国家試験の合格が求められます。
一方、設計士には特定の資格が必要ありません。しかし、実際の業務では建築に関する専門知識やCADなどの技術スキルが求められます。
多くの設計士は、建築学科や専門学校で学んだ後、設計事務所やハウスメーカーなどで実務経験を積みながらスキルを磨いていきます。
建築士と設計士の仕事内容の違い

建築士と設計士には業務内容に大きな違いがあります。
建築士の主な業務と責任
建築士の主な業務は、建築物の設計、工事監理、構造計算、法令チェックなど多岐にわたります。特に重要なのが、建築確認申請に関する業務です。建築物が建築基準法などの法令に適合していることを確認し、責任をもって署名・押印を行います。
また、工事現場での監理業務も重要な役割で、設計図通りに工事が進められているかを確認し、必要に応じて施工者への指示を行います。
建築士は、建築物の安全性や法令順守に関する最終的な責任を負う立場にあり、その業務には高度な専門知識と経験が必要とされます。
設計士の主な業務と役割
設計士は、主に建築物のデザインや詳細設計に携わります。
クライアントの要望をヒアリングし、それを具体的な設計図面やパース(完成予想図)として表現する業務が中心です。3DモデリングソフトやCADを使用して、建築物の外観や内装を設計し、プレゼンテーション資料の作成も行います。
また、設計段階での予算管理や、施工業者との調整なども重要な業務です。デザイン性と実現可能性のバランスを取りながら、クライアントの満足度の高い提案を行うことが求められます。
プロジェクトでの関わり方の違い
建築プロジェクトにおいて、建築士と設計士は異なる役割を担います。
建築士は、プロジェクト全体を法的・技術的な観点から管理し、最終的な責任を負う立場です。設計士は、より具体的なデザインや詳細設計に注力し、クライアントの要望を形にする役割を担います。
大規模なプロジェクトでは、建築士と設計士が協力してプロジェクトを進めることが一般的です。建築士が法令順守や構造的な安全性を確保しながら、設計士が意匠設計やデザインの面でクリエイティブな提案を行うという形です。
キャリアと将来性

それぞれの職業のキャリアステップの例や将来展望をご紹介します。
キャリアステップの例
建築士と設計士のキャリアパスは、それぞれ異なる特徴を持っています。ここでは、一般的なキャリアステップの例を紹介します。
建築士のキャリアパス:
【1】大学の建築学科や専門学校で建築を学ぶ(4年間)
【2】設計事務所やゼネコンなどに就職し、実務経験を積みながら二級建築士の資格を取得(0〜2年)
【3】一級建築士の資格を取得
【4】設計部門のリーダーや管理職として活躍
【5】独立して設計事務所を開設
設計士のキャリアパス:
【1】大学の建築学科や専門学校で建築を学ぶ(2〜4年)
【2】ハウスメーカーや設計事務所に就職(新卒)
【3】CADオペレーターとして経験を積む(1〜2年)
【4】補助的な設計業務を担当(2〜3年)
【5】独立した設計業務を担当(4年目以降)
【6】二級建築士の資格取得を目指す
【7】さらにキャリアアップを目指し、一級建築士の資格取得を目指す
これらのキャリアパスは一例であり、個人の適性や目標、勤務先の方針などによって異なる場合があります。
一級建築士を目指す場合、資格取得までに一定の実務経験が必要となるため、長期的な視点でキャリアを計画することが重要です。
一方、設計士の場合は、就職後すぐに設計業務に携わることができますが、より高度な業務や責任ある立場を目指すには、継続的なスキルアップと経験の蓄積が必要となります。
両者に共通して重要なのは、CADなどの技術スキルの向上、建築関連の法規や最新の設計トレンドに関する知識の更新、コミュニケーション能力の向上などです。これらのスキルを磨くことで、キャリアアップの可能性が広がります。
独立・転職の可能性
建築士として独立する場合、一級建築士の資格を持っているとよりベター。設計事務所を開設する際は、建築士事務所登録を行い、必要な保険に加入するなどの手続きが必要となります。また、顧客獲得や事務所運営のノウハウも重要です。
転職の場合、経験を積んでいるとゼネコン、ハウスメーカー、不動産デベロッパー、官公庁など、幅広い分野で需要があります。
設計士の場合、建築士のような法的な制約がないため、比較的自由に独立することができますが、実績やポートフォリオの充実が重要です。また、CADスキルや3Dモデリングの技術を活かして、設計業務を請け負う形態も増えています。
転職の場合もCADスキルや設計の実務経験を活かして、建設関連企業や製造業など、異なる業界への転職も可能です。また、建築コンサルタントやCADインストラクターなど、設計スキルを活かした関連職種への転職の道が考えられます。
業界動向と将来展望
建築業界は、デジタル化やBIM(Building Information Modeling)の普及により、大きな変革期を迎えています。特に、環境配慮設計やスマートビルディングなど、新しい技術や概念への対応が求められています。
建築士には、従来の専門知識に加えて、デジタルツールの活用や環境性能の評価など、新しいスキルの習得が期待されています。設計士も同様に、BIMソフトウェアの操作や、サステナブル建築の知識など、時代のニーズに応じたスキルアップが必要です。
年収と待遇の比較
建築士と設計士の一般的な年収と待遇をそれぞれご紹介します。
建築士の平均年収と待遇
建築士の年収は、資格の種類や経験年数、勤務先によって大きく異なります。一級建築士の場合、年収700万円前後となるケースも多く、大手設計事務所や建設会社では、さらに高額となる可能性があります。二級建築士は、経験年数に応じて500万円前後が一般的です。
また、資格手当てや残業手当て、賞与など、待遇面も充実している企業が多いのが特徴です。特に、一級建築士の資格取得後は、大幅な待遇改善が期待できます。
設計士の平均年収と待遇
設計士の年収は、経験やスキルレベル、勤務先によって幅があります。設計事務所勤務の場合、年収500万円~400万円前後が一般的です。ただし、優れたデザインスキルや実績を持つ設計士は、より高い報酬を得ることも可能です。
フリーランスの場合、プロジェクトの規模や件数によって収入が変動します。実績のある設計士であれば、年収600万円以上を稼ぐことも可能ですが、仕事の安定性には注意が必要です。
働き方とライフワークバランス
建築士は、一般的に設計事務所や建設会社に勤務し、比較的安定した勤務形態となります。ただし、プロジェクトの進行状況によっては、残業や休日出勤が必要となることもあります。工事監理業務がある場合は、現場への出張も発生します。
設計士の場合、設計事務所勤務であれば通常の勤務時間となりますが、プロジェクトの締切りに向けて残業が増えることもあります。フリーランスの場合は、自身で時間管理が可能ですが、納期との兼ね合いで不規則な働き方となることもあります。
必要な資格と取得までの道のり

先述したように、建築士には一級建築士と二級建築士、木造建築士の資格があり、資格取得までにはステップを踏む必要があります。
一方、設計士は資格がいらない分、スキルを身につけなければなりません。
建築士の種類と取得要件
建築士の資格取得には、実務経験と国家試験の合格が必要です。一級建築士は、大学の建築学科卒業後2年以上の実務経験が必要。二級建築士、木造建築士は、大学の建築学科を卒業していれば実務経験は必要なく、試験内容も一級建築士に比べてやや易しくなっています。
▼あわせて読みたい
設計士に必要な資格
設計士として働く上で、法的に必要な資格はありませんが、スキルを証明する資格として、CAD利用技術者試験やBIM技術者検定などが有用です。また、インテリアコーディネーターやカラーコーディネーターなど、専門分野の資格を取得することで、より幅広い業務に対応できるようになります。
▼あわせて読みたい
資格取得にかかる期間と費用
建築士資格の取得には、相応の時間と費用が必要です。一級建築士の場合受験料は17,000円。合格率は1割と言われており、合格するまでに何年もかかる場合もあります。
受験対策として、通学や通信の講座を利用する場合は、30万円~50万円程度の費用が必要です。二級建築士も同様に、受験料と講習費用を合わせると20万円程度の費用がかかります。
どちらを目指すべきか?選択のポイント

建築士と設計士、どちらを選ぶか迷っている方に向け、職業を選ぶ時のポイントをご紹介します。
適性と必要なスキル
建築士には、法令や構造計算などの技術的な知識に加えて、プロジェクトマネジメント能力が求められます。また、施工業者や行政機関とのコミュニケーション能力も重要です。
設計士の場合、デザインセンスやクリエイティビティが重要です。CADや3Dモデリングのスキルはもちろん、クライアントの要望を理解し、それを形にする提案力も必要です。
自分に合った職業を選ぶポイント
職業選択のポイントとして、以下の要素を考慮することをお勧めします。
- 興味の方向性:技術面に興味がある場合は建築士、デザイン面に興味がある場合は設計士が向いているかもしれません。
- 資格取得への意欲:建築士を目指す場合、国家資格の取得に向けた長期的な学習が必要です。
- キャリアビジョン:独立志向が強い場合、建築士として独立するか、設計士としてフリーランスを目指すかを検討します。
働き方の希望:働き方の希望:安定志向の場合は建築士として企業に勤務する道を、フレキシブルな働き方を希望する場合は設計士としてのキャリアを検討します。
建築・設計のプロフェッショナルへ:実務で活きるCADスキルを習得しよう
建築士・設計士どちらの道を選んでも、CADスキルは必須となっています。2D CADによる図面作成だけでなく、BIMソフトウェアを使用した3Dモデリングも一般的になってきています。
実務では、AutoCADやVectorworks、ARCHICAD、Revitなどの各種CADソフトが使用されており、これらのスキルを習得することで、キャリアの幅が大きく広がります。また、3Dパースの作成ソフトやレンダリングソフトの操作スキルも、付加価値として重要です。
CADオペレーターの派遣・転職はアットキャドへ

アットキャドは、業界トップクラスの求人数を持つ、CADオペレーターやBIMオペレーターに特化した人材派遣・人材紹介サービスです。
20年以上の実績を持ち、スーパーゼネコンや大手設計事務所を含む2,600社以上と取引実績があり、業界トップクラスの求人数を誇ります。自社に設計部を設けているため、実際に図面を描くプロフェッショナルが在籍し、迅速なサポートが可能です。
研修制度も充実しており、初心者から経験者まで幅広く対応。登録から就業後まで徹底したフォローを行いますので安心してお仕事を探すことができます。
さらに、業界トップクラスの求人数があることから、転職のサポートも行っています。未経験からCADオペレーターやBIMオペレーターになりたい場合や、CADオペレーター・BIMオペレーターとしてキャリアアップしたい場合など、さまざまなケースに対応しているので、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
建築士と設計士は、建築業界で重要な役割を果たす職種です。建築士は法的な資格と責任を持つ専門家として、設計士はデザインと設計のスペシャリストとして、それぞれの特徴があります。
職業選択にあたっては、自身の適性や興味、キャリアビジョンを考慮しながら、じっくりと検討することが重要です。また、どちらの道を選んでも、デジタルスキルの習得や継続的な学習が不可欠となっています。
▼コチラの記事もおすすめ