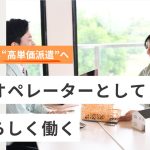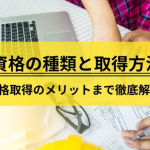建築CAD検定は、建築業界で活躍するために有利な資格のひとつです。
「試験の難易度はどれくらい?」「独学でも合格できる?」「資格を取るメリットは?」といった疑問をお持ちの方に向け、本記事では試験概要・合格率・効果的な勉強法・資格の活かし方を詳しく解説します。
受験を考えている方や、キャリアアップに資格を活かしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
▼あわせて読みたい
▼CADオペレーターの魅力については以下の記事でも紹介しています
目次
建築CAD検定とは?

さっそく建築CAD検定試験の概要を解説します。
建築CAD検定試験の目的と概要
建築CAD検定は、1993年に誕生した日本初の建築CAD資格試験。学生、転職希望者、現役オペレーターなど、建築CADを学ぶ幅広い層の方々が受験しています。
建築設計や施工管理の現場で求められるCADスキルを客観的に評価し、証明するための資格として広く認知されています。
試験の種類は、准1級・2級・准2級・3級・4級(高校の団体受験のみ)です。主催の一般社団法人全国建築CAD連盟(AACL)によると、1級がない理由は「試験方法や採点方法の環境を整備することが容易でない」からとのこと。
また、3級と2級の出題内容・難易度に大きな違いがあることから、2024年10月より新たに准2級が新設されています(一般受験は2025年4月より受験開始)。
受験に使用するCADソフトは、汎用CAD(どのような分野でも利用できる自由度の高いソフト)であれば特に制限はありません。おすすめは、シェアが高く実務にもつなげやすいAutoCADや、無料で利用できるJw_cadです。実際に受験で使用されているソフトはほとんどこの2つが占めています。
受験方法:一般受験と団体受験
受験方法は「一般受験」と「団体受験」の2つ。社会人の方や試験認定校以外の教育機関に通う方は一般受験での受験となります。
受験方法1.一般受験
個人で申し込み、全国の指定会場で受験します。試験は年2回(4月・10月)実施され、准1級は10月のみの実施、4級は対象外です。
受験方法2.団体受験
全国約760校の試験認定校で、年4回(4月・7月・10月・1月)実施されます。准1級は10月のみの実施です。
建築業界での評価と活かし方
建築CAD検定は、建築設計や施工管理の仕事に直結し、転職・就職の際に有利になることもあります。
建築関連のCADスキルを証明する資格として、履歴書や職務経歴書に記載できる点も大きなメリットです。
建築CAD検定の申込方法

建築CAD検定は受験方法によって申し込み手順が異なるため、事前に流れを確認しておきましょう。
建築CAD検定申込の流れ
建築CAD検定の一般受験の申し込みは公式サイトから行い、団体受験の場合は試験認定校を通して行います。一般受験の申込方法は以下の通りです。
- 一般受験申込ページで希望会場を指定後、申込者情報を入力
- 受験料を支払い(クレジットカード決済)
- 「完了する」ボタンを押して申込完了
受験方法は、会場に用意されているパソコンを使用する方法と、自分のノートパソコンを会場に持ち込む方法の2種類から選択します。会場により異なる場合があるので、詳細は一般受験会場一覧にて確認してください。
受験料は准1級が14,700円、2級〜3級が10,500円、高校の団体受験のみの4級が3,150円です(いずれも税込)。
建築CAD検定申込時の注意点
建築CAD検定の申し込み後は、内容の変更ができません。間違いがないか、事前にしっかり確認しましょう。
受験票は試験日前月の中旬に発送されます。試験当日は以下を忘れずに持参しましょう。
- 受験票
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 指定された持ち物(筆記用具・PC持込の場合はACアダプターなど)
建築CAD検定の試験内容、合格基準、難易度
建築CAD検定は、実技試験を通じてCADスキルを評価する試験です。この章では各級ごとの試験内容や難易度を解説します。
建築CAD検定の試験内容
試験は筆記がなく、実技試験のみで構成されています。試験内容は以下の通りです。
- 4級(試験時間2時間):完成図を作成、問題数は3題 ※難易度は3級より低い
- 3級(試験時間2時間):完成図を作成、問題数は4題
- 准2級(試験時間3時間):完成図を作成、問題数は2題
- 2級(試験時間5時間):建築一般図を2面作成
- 准1級(試験時間4時間10分):建築一般図を4面作成
建築CAD検定の受験資格・合格基準
建築CAD検定では、受験資格の規定はありません。合格基準の目安は次のように定められていますが、試験問題の難易度などを勘案し若干上下することがあります。
- 4級:200点満点中、130点~140点
- 3級:200点満点中、140点~150点
- 准2級:正解率75~80%
- 2級:250点満点中、190点~200点
- 准1級:4図面すべて完成(未完成の箇所があれば不合格)
建築CAD検定の難易度と合格率
建築CAD検定の難易度は、級によって大きく異なります。特に准1級は非常に難しく、年により合格率も変動しています。
初心者でも4級・3級は比較的取得しやすいですが、2級以上になるとより高度な実技スキルが求められ、実務経験があると有利になります。
2001年〜2023年の合格率は以下の通りですので参考にしてください。(参考:一般社団法人 全国建築CAD連盟)
- 4級:約90%
- 3級:約60~70%
- 准2級:新設のためデータなし
- 2級:約50~60%
- 准1級:約10%
なお合格者には希望者を対象に認定証が発行されます。Web上で発行するため、ダウンロードして保存ができ、紛失した際も無料で何度でも再発行することができます。
建築CAD検定の効果的な勉強法と対策

建築CAD検定の合格を目指すには、効率的な学習計画が欠かせません。独学での対策方法やスクールの活用方法、試験対策に役立つ教材などを詳しく紹介します。
独学 vs スクールのメリット・デメリット
受験の準備には、独学で勉強する方法、スクールを利用する方法があります。
独学の場合、コストを抑えながら自分のペースで学習できるメリットがありますが、学習スケジュールを管理する自己管理能力が求められます。
一方、スクールに通う場合は、短期間で集中的に学ぶことができ、講師から直接指導を受けられる利点があります。受講費用と効率のバランスを考えてコースを選びましょう。
▼あわせて読みたい
おすすめの学習教材
効果的な学習のためには、公式ガイドブックや過去問題集の活用が不可欠です。
特に、全国建築CAD連盟公認の『建築CAD検定試験問題集』は、試験要項や採点基準、解法例が詳しく解説されており、試験対策に役立ちます。
合格への近道は何といっても過去問題を繰り返し解くこと。出題傾向を把握でき、試験本番に向けた実践力を高めることができます。
さらに、オンライン講座を活用することで、実技試験のポイントを効率よく学ぶ手もあります。オンライン講座には、日建学院やUdemyなどの受験対策講座があります。
合格率を上げるための学習プラン
学習プランを立てる際には、試験日から逆算して4〜6ヶ月前からの学習開始を目安にするとよいでしょう。
特に実技試験では、反復練習を重ねることで作業スピードと精度を向上させることが重要です。また、模擬試験を受け、本番の試験形式に慣れておくことで、試験当日のパフォーマンス向上につながります。
ぜひ受験の準備に取り掛かる前に、学習プランを立ててみてください。
建築CAD検定の取得メリットと仕事への活かし方

資格は、取得後にどのようにキャリアに活かすのかが重要です。本章では、転職やキャリアアップの可能性、実務での活用方法、受験者の体験談などを交えながら、建築CAD検定がどのように役立つのかを解説します。
転職・キャリアアップへの影響
建築CAD検定に合格すると、未経験者でもCADオペレーターとして就職につながりやすくなります。特に、建築設計事務所やゼネコン、工務店では、CADスキルを持つ人材が求められるため、資格取得は強みとなるでしょう。
また、設計補助職や施工管理職を目指す際にも、建築CAD検定が一定のスキルを証明する資格として評価され、キャリアアップの可能性を高めることができます。
実務での活用方法
建築CAD検定は、建築業界での実務スキルの証明として非常に有効です。建築図面の作成・修正ができる人材として評価されるため、業務の幅が広がります。
例えば、建築設計事務所では、施工図の作成や意匠図の編集業務を担当することが可能になります。また、ゼネコンや工務店では、建築施工管理に必要な図面を理解し、調整業務をスムーズに進めることができるようになります。
受験体験談・合格者の声
建築CAD検定を取得したことで、実際の仕事やキャリアにどのような影響を与えるのか、合格者の声を紹介します。
【現場監督としての活用】
「CAD業務に関わる際に大変役立っていると実感しています。施工図面をスムーズに読み取り、修正するスキルが向上し、現場の作業効率が格段に上がりました。」
【学生時代の取得が自信に】
「学生時代に資格を取得したことで、社会に出る際の大きな自信につながりました。面接でも資格をアピールでき、建築設計の仕事に就くきっかけになりました。」
参考:https://www.aacl.gr.jp/12goukakusha01.html
建築・設計業界では、建築需要の高まりから専門知識と高度なCAD技術を持つ人材の育成が急務であり、建築CAD検定は企業からも高く評価されている資格です。
他のCAD資格との比較:どちらを取得すべき?
CAD関連のどの資格にチャレンジするかを決めるには、自分のキャリア目標に合ったものを選ぶことが大切です。建築CAD検定は、建築分野に特化しているので、建築業界でのキャリアを考えている方には最適です。
一方で、他の業界でも通用するスキルを証明したい場合は他の選択肢も検討するとよいでしょう。よく比較されるCADの資格2つをご紹介します。
▼あわせて読みたい
他のCAD資格との比較1.CAD利用技術者試験
CAD利用技術者試験は、業界を問わず幅広いCADスキルを評価する資格です。
筆記試験も含まれ、CADの基礎知識を問われるため、建築業界に限らず製造業や土木業界でも活用できます。幅広い業界でCADスキルを活かしたい方にはCAD利用技術者試験がおすすめです。
▼あわせて読みたい
他のCAD資格との比較2.CAD実務キャリア認定制度
CAD実務キャリア認定制度は、建築業界だけでなく、製造・土木・機械設計など多分野で評価される資格です。2D・3Dの両方の試験があり、より実務に即した設計・製図スキルを証明できます。
そのため難易度は高めですが、実務経験を活かしながらキャリアアップを目指す方におすすめです。
建築CAD検定を活かした派遣・転職はアットキャドへ

アットキャドは、業界トップクラスの求人数を持つ、CADオペレーターやBIMオペレーターに特化した人材派遣・人材紹介サービスです。
20年以上の実績を持ち、スーパーゼネコンや大手設計事務所を含む2,600社以上と取引実績があり、業界トップクラスの求人数を誇ります。自社に設計部を設けているため、実際に図面を描くプロフェッショナルが在籍し、迅速なサポートが可能です。
研修制度も充実しており、初心者から経験者まで幅広く対応。登録から就業後まで徹底したフォローを行いますので安心してお仕事を探すことができます。
さらに、業界トップクラスの求人数があることから、転職のサポートも行っています。未経験からCADオペレーターやBIMオペレーターになりたい場合や、CADオペレーター・BIMオペレーターとしてキャリアアップしたい場合など、さまざまなケースに対応しているので、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ:建築CAD検定を取得するべき理由
建築CAD検定は建築業界でのスキル証明に最適な資格で、適切な学習をすれば独学でも十分合格可能です。
受験では合否だけに注目してしまいがちですが、合格に向けて自身の知識やスキルを棚卸しして、新しい内容を勉強すること自体が実務スキルの向上につながります。
資格とスキルを活かして、CADオペレーターとしてのキャリアアップを目指しましょう。
▼コチラの記事もおすすめ